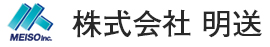三献茶に学ぶ、“今”に寄り添う力
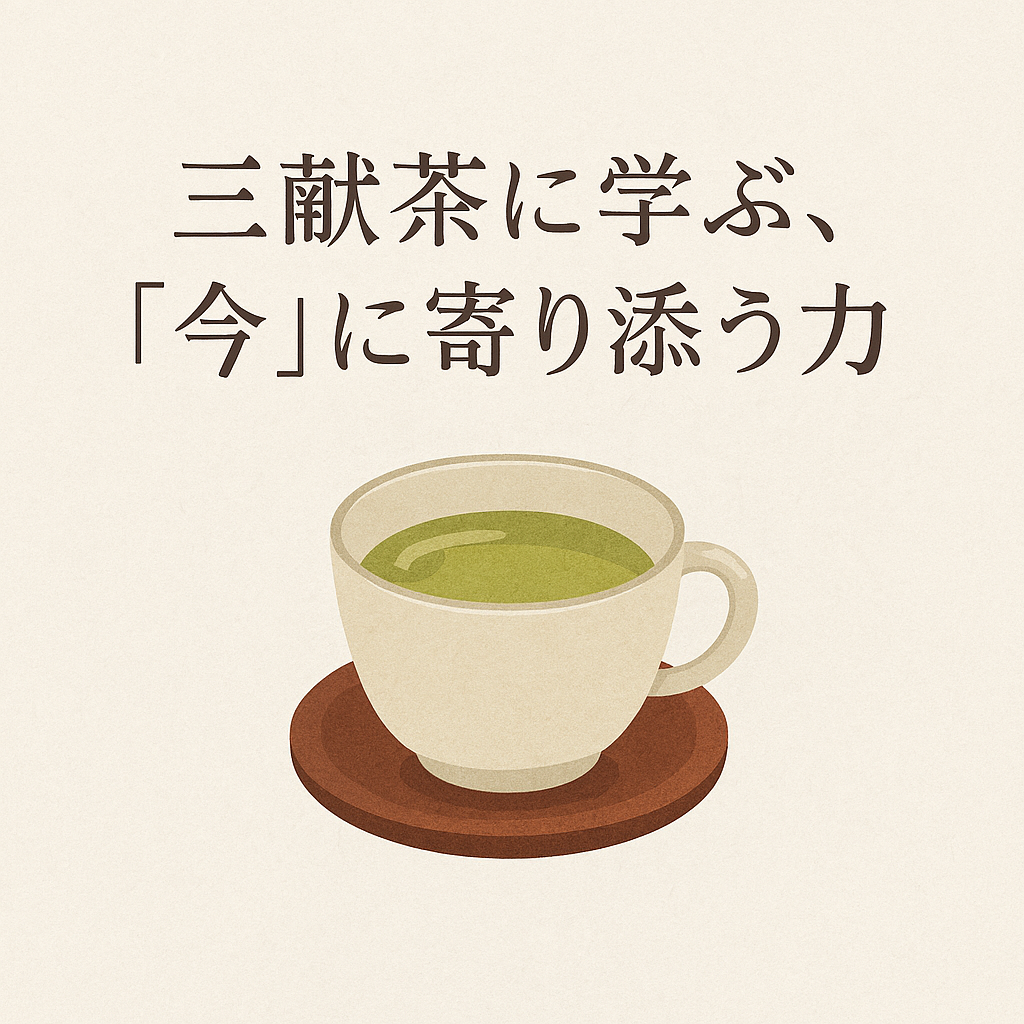
本社の本橋です。
みなさんは、『三献茶』って逸話を知っていますか?
このお話……とっても素敵だな!と思ったので紹介させてください🌼
『三献茶』てなあに?
秀吉が鷹狩りの帰りに寺へ立ち寄り、喉の渇きを訴えたときに、寺の童子だった石田三成が出した3杯のお茶🍵
• 1杯目:ぬるめのお茶をたっぷり → 喉の渇きを癒すため
• 2杯目:少し熱めのお茶を半分 → 香りと味を楽しむため
• 3杯目:熱々のお茶を少量 → 出発前に軽く味わうため
それぞれのお茶の温度と量が、秀吉の状態にぴったりだったというこの話は、今も“気配りの極意”として語り継がれています。
私はこの話を初めて聞いたとき、「気配りってこんなに深いものなんだ(゚o゚;」と驚きました。
これはただの“おもてなし”ではなく、相手の様子を見て、何が必要かを考えて、言われていないことまで察して動くということ。
それって、仕事にもすごく通じる気がしています。
🍵 三献茶を通して伝えたいこと
① 気配りは、相手の“今”に寄り添うこと
三成は、秀吉の喉の渇き、体の疲れ、そして出発のタイミングまで読み取って、お茶の温度と量を変えました。
これは「気を利かせる」ではなく、“相手の状態に合わせて動く”という本質的な配慮です。
② 信頼は、静かな行動の積み重ねで生まれる
三成は何も語らず、ただ3杯のお茶を出しただけ。
でもその行動が、秀吉の心を動かし、信頼につながりました(結果、家来になった)。
③ 指示を超えて、意味を考えることが価値になる
秀吉は「茶を持ってこい」としか言っていません。
でも三成は、その言葉の“背景”を読み取り、最適な対応をしました。
④ 気配りは、技術ではなく“感性”
三成の対応はマニュアルではできないと思います。
それは、相手を見て、感じて、動く“感性”の力だと思います。
石田三成は、秀吉に言われた通りにお茶を出したわけではありません。
彼は、秀吉の疲れ、喉の渇き、立ち上がるタイミングを“感じとって”、
それに合わせてお茶の温度と量を変えました。
それは、誰かに教わったわけじゃなく、彼自身が磨いてきた感性だったんだと思います。言われたことをただこなすのではなく、相手の様子を見て、今必要なことを考えて動く。それって、日々の仕事や生活、そして人との関わりの中で、すごく大事なことだと思うんです。
たとえば、誰かが忙しそうなときに「あとで話そうか」と声をかけること。
会議で発言しづらそうな人に「どう思いますか?」と促すこと。
そういう小さな気配りが、安心感や信頼につながっていく気がします。
気配りって、誰かに「こうすればいいよ」と教わるものじゃないし、教科書で学ぶようなものでもない。それよりも、日々の生活の中で「この人、今どんな気持ちかな?」って考えることの積み重ねだと私は思います。
それが、少しずつ自分の中の感覚を磨いてくれるんじゃないかなと思います。
うまくいかなかった対応も、誰かの優しさに触れた瞬間も、全部が磨きの布になる。
この話を聞くたびに思います。
気配りは、育てるものじゃなくて、日々磨くもの。
「育てる」と「磨く」って、似ているようで違いますよね。
「育てる」のは、まだ芽が出ていないものに水や光を与えて、時間をかけて伸ばしていくこと。
「磨く」のは、すでにある素材を、丁寧に研ぎ澄ませて光らせていくこと。
気配りは、後者だと思うんです。
誰かの表情に気づく力、空気の変化を感じる力、沈黙の意味を察する力。
それって、みんなが持っているもの。でも、意識して使わないと、曇ったままになってしまう。
少年だった石田三成が、秀吉の状態に合わせて3杯のお茶を出したあの場面。
あれは、誰かに教わったわけじゃなく、彼自身が磨いてきた感覚だったんじゃないかと。
気配りは、育てるものじゃなくて、磨くもの。
みんなが持っているものだけど、忘れがちな力。
そして気配りは、信頼をつくる静かな力になるんだなって、私は思います。
だからこそ、誰かの“今”に寄り添う一杯を差し出せるように、
私も日々、自分の感覚を磨いていきたいと思っています。